「毎朝お弁当を作るのが大変…」「手作りしたいけれど時間がない!」「でも毎日コンビニでお弁当買うのもあきちゃう」そんな悩みを抱えている皆さんへ。冷凍宅配弁当を上手に活用すれば、忙しい朝でも簡単に美味しいお弁当が作れます。本記事では、冷凍宅配弁当を使った簡単アレンジ術や時短テクニックをご紹介。あなたのお弁当作りがもっと楽しく、負担の少ないものになるはずです!
冷凍宅配弁当を活用するメリット

冷凍宅配弁当って、最近よく聞くけど実際どうなの?使えるの?疑問に思っている人もたくさんいると思います。そこでまずは、冷凍宅配弁当を使うメリットを見ていきましょう!
忙しい朝でも時短でお弁当作り
冷凍宅配弁当の一番のメリットは、何より調理の簡単さ。レンジで温めるだけでそのまま食べられ、おかずを作る手間がなくなるので、朝の準備時間を大幅に短縮できます。準備は温めてお弁当に詰めるだけ。洗い物も減らせるので忙しい朝には嬉しいですね。
レンジでチンで簡単調理!
お弁当箱に詰めるだけ!
朝の時間は1分1秒が大切。でも、できるだけお弁当を持っていきたい。そんな時には簡単に作れる冷凍宅配弁当はとても強い味方ですね。
栄養について、しっかり考えられている
冷凍宅配弁当は、管理栄養士が監修しているものが多く、たんぱく質・食物繊維・ビタミンなどバランスの取れた食事を手軽に摂ることができます。偏った食事になりにくく健康管理にはぴったり。品目数も多いので、飽きのこないラインナップが魅力です。和食だけじゃなく洋食や中華などメニューも豊富。ワンパターンになりがちなお昼ごはんが、飽きのこないバリエーションに富んだ魅力的なお昼ご飯に変身します。
管理栄養士が栄養をチェック!
バリエーションに富んだメニュー
塩分やカロリーが調整しやすい
自炊やコンビニ弁当では塩分やカロリーが高くなりがちですが、冷凍宅配弁当は調整されたメニューが多いです。メニューにはたんぱく質量や糖質、脂質の量などもしっかり書かれているので、高たんぱく・低カロリーなど、自分の体調や目的に合った食事を選べます。減塩食や糖質制限に特化したお弁当もあるので、ダイエットや健康管理をしたい人に最適です。
体調や目的にあった食事が簡単にとれる
コストパフォーマンスが良い
一食あたり500~800円程度のものが多く、外食やコンビニ弁当を購入するよりも、冷凍宅配弁当を活用したほうがコストを抑えられる場合があります。コンビニ弁当は安く買おうとすると量が少なくワンパターンに。いろいろ食べようとすると意外と高くつきます。外食すると1,000円くらいは軽くしますし、ワンコインで食べられるところだと、どうしてもメニューが同じになってしまいます。
1食あたり500円弱~
冷凍宅配弁当は、まとめて購入することでお得に利用できるサービスも多くあるので、うまくサービスを活用するとさらにお得に利用できますね。
冷凍宅配弁当のデメリット
メリットをみてきましたが、やっぱりデメリットも気になります。ここでは、冷凍宅配弁当の気になるところを見てみましょう。
・コストがかかる
・味や食感に好みが分かれる
・ボリュームが足りない場合がある
・冷凍庫のスペースをとる
・すべてが無添加とは限らない
コストがかかる
メリットでコストパフォーマンスが良いとかきましたが、それは外食にくらべてのお話でした。外食よりは安くなるものの、自炊と比べるとやはり一食あたりのコストは高くなりがち(500~800円程度)。まとめ買いで安くなる場合もありますが、定期的に購入するとなるとひと月の費用がかさむ場合もあります。
味や食感に好みが分かれる
冷凍食品特有の食感(例えば、野菜が少し柔らかくなるなど)が苦手な場合は気に入らないことも。また、メーカーによって味付けの濃さや風味が異なります。自分で作れば自分好みの味にできますが、お弁当によっては好みに合わないこともあります。
ボリュームが足りない場合がある
冷凍弁当によってはダイエット向けにカロリーコントロールされているものや、制限食用などもあり、食べる量が多い人には物足りないことも。冷凍弁当を選ぶ時には、どれくらいの量なのかチェックが必要です。足りない分はスープやサラダを追加するなどの工夫が必要になってくることも。
冷凍庫のスペースを取る
まとめ買いすると冷凍庫の収納スペースをかなり占領する場合があります。一人暮らしの小さな冷凍庫だと、他の食材が入りにくくなることも。定期的に購入する場合は、どれくらいの期間で何個届くかも考えましょう。
すべてが無添加とは限らない
添加物を気にする人にとっては、一部の商品に保存料や調味料が入っていることがデメリットになります。自炊ではないので、どうしても気になる方も。無添加やオーガニックの冷凍弁当を選べば解決できますが、価格が高めになることが多いです。
デメリットを補う方法
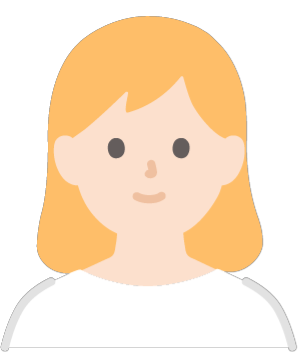
冷凍宅配弁当をお弁当で持っていきたいけど、デメリットが並ぶと
どうしても気になってしまいます。



デメリット、気になりますよね?
気になるデメリットを少しでも減らすために
こんな方法はいかがでしょう?
✅コストが気になる → まとめ買いで割引を利用する、クーポンを活用する。
✅ 食感や味が気になる → 口コミをチェックし、自分の好みに合うメーカーを選ぶ。
✅ ボリュームが足りない → スープやサラダ、果物を追加する。
✅ 冷凍庫が狭い → 小分けに注文する、収納を工夫する。
✅ 無添加が気になる → 原材料表示を確認し、添加物が少ないものを選ぶ。
総合的に見ると、冷凍宅配弁当は便利で時短にもなりますが、コストやボリュームの問題などを考慮しながら活用するのがポイントですね!
あなたのライフスタイルにはどんな活用方法が合いそうですか?
冷凍宅配弁当、こんな使い方がおすすめ!


冷凍宅配弁当+ごはんで簡単ランチ
冷凍宅配弁当は主菜と副菜がバランスよく含まれています。お弁当によっては5種類のおかずがはいっているものも。お弁当用に何種類もつくるのはたいへんですよね。冷凍宅配弁当を解凍して、ごはんを追加するだけで、栄養バランスの良いお弁当が簡単に完成します。電子レンジでチンするだけなので、忙しい朝でもお弁当作りは安心です。



お弁当の内容を考える手間も、食材を買って作る手間もないから本当に気楽です。朝、10分あったらすぐに作れてしまうのが魅力。
おかずを組み合わせてアレンジ
冷凍宅配弁当のおかずがちょっと少ないなと思ったら、作り置きおかずやサラダ、スープやお味噌汁を組み合わせれば、手軽にバリエーションを増やせます。例えば「主菜は冷凍宅配弁当、副菜は自分で用意」といった使い方も◎。お家で炊いたご飯のかわりに、コンビニでおにぎりやパンを買ってボリュームアップもできます。アレンジすることで、量の調節や味のバリエーションも増えますね。



ごはんを炊き忘れてた時も、おかずだけ持っていてコンビニでおにぎり追加するだけで、しっかりしたお昼ご飯が完成します。とっても便利。
忙しい日や疲れた日に活用
週に2~3回、特に「仕事が忙しい日」や「料理をする気力がない日」に利用すると、無理なく続けられます。毎日ではなく、週に数回だけ冷凍宅配弁当を取り入れることで、飽きずに利用しやすくなりますし、コストや栄養バランスの調整もしやすくなります。予定にあわせて、助っ人的につかうのがポイントですね!忙しい朝に作れなかったときの”予備”として、冷凍宅配弁当を1~2個冷凍庫に入れておくのも安心です。



私も、夕飯の残りをお弁当にする時もあるし、お友達と外食する時もあるので、毎日は使っていません。でも冷凍宅配弁当があると思うと、気軽にお弁当にできるので楽ですね。
ダイエット、調整食で健康管理
ダイエット中の食事は脂質や糖質が気になるもの。でも糖質少なめのお弁当を自分でいつも作るのはたいへん。
健康管理のために減塩したい。これも減塩して美味しいお弁当を毎食作るのはとてもたいへん。
でも冷凍宅配弁当なら、糖質も塩分も管理栄養士が監修したメニューで楽に管理できます。



最近、体重が増えたのでダイエットしたいけれど、健康的にバランスよく食べないと体をこわしそう。例えばワタミの宅配だと、必ずたんぱく質や脂質量がわかるから、ダイエットの食事制限にかかせません。
冷凍宅配弁当の向き・不向き
これまで冷凍宅配弁当のメリットやデメリット、おすすめの活用法をみてきましたが、結局どんな人が使えばいいの?と疑問にぶちあたりました。向いてる人と向かない人、見比べて、じゃあ自分は?と考えてみてくださいね!
向いている人
- 朝の時間がなく、お弁当作りに手間をかけたくない人
- バランスの良い食事を手軽に用意したい人
- 料理が苦手だけど、手作り弁当を持参したい人
- 料理する時間がない日や、疲れた日の負担を減らしたい
- 外食を減らして健康管理をしたい
向いていない人
- 毎日完全手作りのお弁当にこだわりたい人
- 添加物や保存料を気にする人
- コストを最小限に抑えたい人(冷凍宅配弁当は多少割高な場合がある)
まとめ
冷凍宅配弁当を活用すれば、忙しい朝でも簡単にお弁当を準備できます。お弁当用に詰めるだけ、アレンジして楽しむなど、工夫次第で手軽に美味しいお弁当が作れます。
でも、冷凍宅配弁当って実はたくさんあるんです。何を基準に選ぶのか、じっくり考えてみては?
そして「毎朝のお弁当作りが大変…」「楽にお弁当を作りたい」と思っているあなた、冷凍宅配弁当を活用して、手軽に美味しいお弁当を作ってみませんか?
▼冷凍宅配弁当が気になる方はこちら▼



